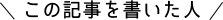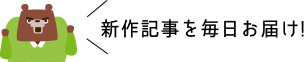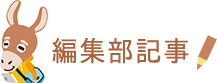風来坊のハンドシェイク
映画「男はつらいよ」の舞台となった葛飾・柴又の一部の地域が国の重要文化財的景観に選定され、保護の対象とするよう文部科学相に答申されたという。
この重要文化財的景観の定義としては「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」となり、全国ですでに51件が選定されているが、東京都内が対象となるのは初だそうだ。
この認定が「男はつらいよ」に漂う人情味の溢れる街の匂いを、現代の日本に少しでも残してくれる事に寄与するのであればファンとしては非常に嬉しい。そもそも30年近く続いた「男はつらいよ」シリーズ自体がすでにある面で「我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」なのかもしれない。今の社会からはすっかり失われてしまった多様な風習や情緒なども作中に含んでいる稀なシリーズものだと考えられる。
「男はつらいよ」といえばマンネリズムの美学ともいえる形式美がある。たとえばオープニングの音楽にのせて必ず挿入される寅さんの台詞「私、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯をつかい、姓は車、名は寅次郎、人呼んでフーテンの寅と発します」はあまりにも有名だが、これも日本から失われた習俗の一つだと思う。
仁義を切るというプロトコル
これはいわゆる「仁義を切る」というもので、渡世人が初対面の相手と交わす挨拶のことである。これは特殊な形式に則った挨拶で、オープニングの寅さんの台詞はその導入部分にあたる。そこから長々と自分の所属するコミュニティのことや自分が何者なのか、そしてステータスや常識をわきまえている事、暗号的要素などをまとめていっぺんに伝えるという、まさに「名刺代わり」ともいえる識字率が低かった時代ならではの身分証明法なのである。
「男はつらいよ」で寅さんが正式な形で仁義を切るのは、葛飾柴又に出戻ってきて、その界隈の顔役らしき人たちに挨拶をする第1話のみだったはずだが、かつては一言でも言い誤ったりと、所作に間違いがあった場合は「騙り」とみなされ、斬りつけられることもあったというから、かなり緊張感のある挨拶だ。
その代わりに淀みなく仁義を切れれば、その土地土地の親分からお世話になる事ができたそうだ。なんともユニークな風習である。(その所作・口上などについては舞台演出的な要素も加わっているものが一般的に認知され伝わっているだろうから、実際どのように行われていたかについては不明な部分も多いのではないかと思われる)
その名残としてビジネスシーンで「関係部署に仁義を切っておいて」みたいに、ことを成す前に、影響がありそうな関係者に対し事前に断りの挨拶を入れておくように、というニュアンスで使うことはあったが、今となっては死語になりかけているのかもしれない。
特定の相手とだけ交わす挨拶であり、暗号的な要素もあり、また間違いがあってはいけないということで、海外のスポーツ選手同士が交わすあの難易度の高いハイタッチのような「ハンドシェイク」というコミュニケーションがもしかすると「仁義を切る」と類似性の高いもののような気がする。
今後、若い世代を中心に日本でも流行していくように思われる。そう考えるとこの手のコミュニケーションは、景観地とは違って失われることはなく、形式は異なってもその本質的な要素が社会からなくなることはないような気がする。